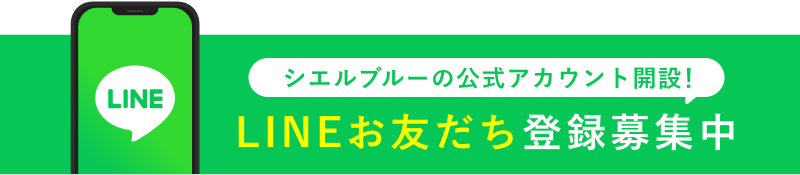その他
カーポートの台風対策完全ガイド!補強方法と被害を最小限に抑える具体策

台風シーズンが近づくと、多くの方が「カーポートが飛ばされないか」と不安に感じます。実際、台風による住宅被害の中でも、カーポートの破損や飛散は非常に多く報告されています。
カーポートは構造上、風の影響を受けやすく設計されているため、適切な対策を講じなければ大きな被害を招く可能性があります。この記事では、台風からカーポートを守るための効果的な対策方法を、プロの視点からわかりやすく解説します。
目次
台風がカーポートにもたらす影響

台風被害が多い地域
日本は台風の通過が非常に多い国です。特に台風上陸回数が多いのは以下の地域です。
- 1位:鹿児島県(42回)
- 2位:高知県(26回)
- 3位:和歌山県(24回)
沖縄県は小さな島を横切ると「通過」と分類され、上陸としてカウントされないため、ランキングには入っていませんが、台風の影響を非常に受けやすい地域です。一般的に、8月〜9月は台風が最も発生する時期となっています。
台風による住まいへの主な被害
台風が住まいにもたらす代表的な被害は以下の5つです
- カーポートの飛散・破損
- 窓ガラスの破損
- 屋根の破損
- 飛来物による外壁やフェンスの損傷
- 雨樋の破損・詰まり
カーポートは特に大きなサイズのエクステリアであるため、強風で飛ばされると周辺の住宅や施設に甚大な被害をもたらす可能性があります。カーポートの被害を防ぐことは、自宅だけでなく近隣の安全を守ることにもつながるのです。
カーポートの構造と台風耐性
 <
<
カーポートが飛びやすい理由
まず理解すべき重要なポイントは、カーポートの屋根は意図的に外れやすく設計されているということです。
一見すると頑丈そうに見えるカーポートですが、実際は屋根材が複数のパネルで構成されており、強風時にはこれらが外れるようになっています。これは、強風の際に屋根だけが外れることで、支柱などカーポート本体の大きな破損を防ぐための設計なのです。
カーポートの屋根が外れにくいように固定してしまうと、支柱ごと破損したり、倒壊したりするリスクが高まります。つまり、屋根が外れるのは安全機能の一部と考えることができます。
カーポートの3つの基本構造
カーポートには主に3つの基本構造があり、それぞれ台風耐性が異なります。
1. 片側支持タイプ
特徴:
- 柱が片側のみに配置
- 屋根は片流れになっている
- 開放感があり、見た目がスッキリしている
台風耐性:
- 3タイプの中で最も耐性が低い
- 柱の数が少ないため安定感に欠ける
- 台風対策が特に必要
2. 両側支持タイプ
特徴:
- 屋根の両側に柱がある
- 2〜3台の車を停めるスペースも確保可能
- 安定感がある構造
台風耐性:
- 片側支持タイプより耐性が高い
- 柱が多いため安定している
- 台風の多い地域におすすめ
3. 後方支持タイプ
特徴:
- 車の後方にのみ柱がある
- サイドに柱がなくスッキリとした外観
- おしゃれな見た目が人気
台風耐性:
- 両側支持タイプより耐性が低い
- 後方の柱のみで支える構造
- デザイン性と耐久性のバランスを取った構造
屋根材の種類と特性
カーポートの屋根材には主に4種類あり、それぞれに特徴があります。
| 屋根材の種類 | 特徴 | 台風耐性 |
| ポリカーボネート | 軽量で透明感あり、採光性が高い | 強度は高いが風であおられやすい |
| FRP | 熱遮断性に優れ、夏場の温度上昇を抑える | 中程度の耐性 |
| スチール折版 | 折り曲げ加工で強度を高めた金属屋根 | 台風や積雪に強い最も耐性が高い |
| アルミ樹脂複合板 | 防火性能が高く、耐久性がある | 比較的耐性が高い |
台風対策を重視するなら、スチール折版やアルミ樹脂複合板が適していますが、スチール折版は光の透過性が低いため、カーポート下が暗くなるというデメリットもあります。
カーポートの台風対策3つのケース

カーポートの台風対策は、状況によって3つのケースに分けられます。それぞれのケースに合わせた最適な対策を見ていきましょう。
ケース1:新規設置時の台風対策
新しくカーポートを設置する場合は、最初から台風に強い構造を選ぶことが最も効果的です。
台風に強いカーポートの選び方
1.耐風圧強度をチェック
・一般的なカーポートの耐風圧強度は風速38m/秒相当
・台風が多い地域では風速46m/秒相当のものが望ましい
・メーカーのカタログで確認すること
2.両側支持タイプを選ぶ
・片側支持タイプより安定性が高い
・特に台風が多い地域では強く推奨
3.スチール折版の屋根材を検討
・強風や大雪にも耐える強度がある
・ただし、採光性は低下する点に注意
4.設置場所を検討
・風の通り道や崖上など風が強い場所は避ける
・片側支持の場合は風上側に柱を配置
設置向きの工夫
カーポートを設置する際は、地域の風向きも考慮しましょう。家の形状によって風の流れは変わりますが、一般的に風が吹き込む側に柱を配置することで、カーポート自体の破損を防ぐことができます。
ケース2:既存カーポートの補強
すでにカーポートを設置している場合は、以下の方法で補強が可能です。
1. 母屋補強材の設置
メリット:
・カーポート本体の強度を大幅に向上させる
・台風による構造自体の損傷リスクを低減
デメリット:
・カーポートの一時的な分解が必要
・専門業者による施工が必要なことが多い
設置方法: カーポート母屋(屋根部分の骨組み)の中に補強材を入れます。中が空洞になっている部分に補強材を挿入し、折れにくくする工法です。
2. 屋根ホルダーの設置
メリット:
・屋根材が飛散するのを防止
・取り付けが比較的簡単
デメリット:
・片側支持タイプには向かない(ホルダーだけでは不十分)
・屋根材の強度によっては効果に限界がある
設置方法: カーポートの屋根部分を押さえ込むように設置し、ビスで固定します。両支持タイプのポリカーボネート屋根におすすめです。
3. サポートの設置(固定式)
メリット:
・片側支持タイプでも両側支持タイプ並みの安定性を獲得
・構造自体を強化できる
デメリット:
・見た目が変わる
・設置スペースが必要
設置方法: 片側支持タイプのカーポートの柱がない部分に、後付けで柱を設置します。固定式は柱を固定したままになるため、片側支持タイプでも両側支持タイプのように使用できます。
注意点: 補強は、メーカー廃盤やメーカー機種が不明な場合など、商品や状態によっては対応できないことがあります。事前に専門業者に相談することをおすすめします。
ケース3:台風直前の緊急対策
補強工事をする時間や予算がない場合でも、台風の直前にはできる対策があります。次章で詳しく解説します。
台風直前にできる応急対策

台風が接近している時には、以下の応急対策を検討しましょう。費用をかけずにできる対策ですので、ぜひ実践してみてください。
1. カーポート周辺の小物を室内に移動
カーポートの周りには、子どものおもちゃやガーデニング用品、自転車の空気入れなど、様々な小物が置かれていることが多いものです。これらは風で飛ばされやすく、カーポートにぶつかってダメージを与える可能性があります。
具体的な対策:
- すべての小物を室内または倉庫に片付ける
- 大型の鉢植えや自転車など移動できないものは、しっかり固定する
- ゴミ箱なども風で転がる可能性があるため注意
2. カーポートの屋根材を取り外す
カーポートの屋根は外れやすい仕組みになっていますが、強風で飛ばされると周囲に被害を及ぼす危険があります。特に樹脂製の屋根材など取り外しが容易なものは、台風前に取り外しておくことをおすすめします。
取り外し手順:
- 脚立を安定した場所に設置
- 屋根材を固定しているビスやボルトを確認
- 必要な工具で固定部分を外す
- 屋根材を慎重に降ろす
- 取り外した屋根材は安全な場所に保管
注意点: 屋根材の取り外しは高所作業となり危険を伴います。経験がない方は無理せず、専門業者に依頼することも検討しましょう。
3. 着脱式サポートの設置
片側支持タイプや後方支持タイプの場合、柱のない部分に着脱式のサポートを設置することも有効です。着脱式なら、台風時にのみ設置して普段はスッキリとした見た目を維持できます。
メリット:
- 大掛かりな工事が不要
- 必要なときだけ設置できる
- 普段は見た目を損なわない
設置方法:
- サポート取り付け位置を決める
- 地面にアンカーを設置(事前準備が必要)
- サポート柱を取り付ける
- 屋根部分と柱をしっかり固定
4. フックボルトやビスの緩みを確認
カーポートの各部を固定しているボルトやビスに緩みがあると、強風で揺れた際にさらに緩みが大きくなり、ひび割れや破損の原因となります。定期的な点検と台風前の確認が大切です。
チェックポイント:
- 屋根材を固定している部分
- 支柱と骨組みの接合部
- 基礎と支柱の接合部
補強方法:
- 緩んでいるボルトやビスを確認
- 適切な工具で締め直す
- 劣化している場合は新しいものに交換
定期点検の目安: 年に2回程度(台風シーズン前と冬の前)を目安に点検すると、劣化や緩みを早期に発見できます。
カーポートが台風で壊れた場合の対処法

万全の対策をしていても、想定を超える台風の猛威によってカーポートが破損することもあります。被害が発生した場合の適切な対処法を理解しておきましょう。
被害状況の確認と記録
台風が過ぎ去り、安全が確認できたら、まずは被害状況を確認します。
確認ポイント:
- 屋根材の破損、飛散状況
- 支柱や骨組みの損傷
- 周辺への被害の有無
記録方法:
- 複数の角度から写真撮影
- 損傷箇所を詳細に撮影
- 周辺の被害状況も記録
これらの記録は、保険請求や修理の際に重要な証拠となります。
飛散した部品の回収
カーポートの屋根や部品が飛散している場合は、速やかに回収しましょう。放置すると二次被害や怪我の原因になります。
回収時の注意点:
- 安全な服装と手袋を着用
- 破損した部品の鋭利な部分に注意
- 高所にある部品は無理に回収せず、専門業者に依頼
火災保険の確認と申請
台風によるカーポートの破損は、火災保険の補償対象となる可能性があります。契約内容を確認し、補償対象であれば速やかに保険会社に連絡しましょう。
保険適用の可能性:
- 火災保険の基本補償に「風災」が含まれていれば対象になることが多い
- 「エクステリア設備」として補償されるケースが一般的
- 免責金額(自己負担額)が設定されている場合もある
申請手順:
- 保険会社に連絡(できるだけ早く)
- 現場検証の日程調整
- 被害状況の写真や修理見積もりの提出
- 保険金の支払い手続き
注意点: 自分のカーポートが原因で近隣に被害を与えた場合は、火災保険ではなく個人賠償責任保険の対象となる可能性があります。
修理や交換の検討

被害状況に応じて、修理か交換かを検討します。
修理を検討するケース:
- 屋根材の一部が破損した程度
- 支柱や骨組みに大きな損傷がない
- 製造から年数が経っていない
交換を検討するケース:
- 複数箇所に大きな損傷がある
- 支柱や骨組みが変形している
- 経年劣化が進んでいる
修理や交換は専門業者に依頼することをおすすめします。特に構造部分の損傷がある場合は、安全面からも専門家の判断が必要です。
福岡市で注意すべき台風対策
福岡市は九州北部に位置し、台風の通過ルート上にあることが多い地域です。福岡市内でもエリアによって風の強さや方向が異なるため、地域特性に合わせた対策が必要です。
福岡市の台風特性
福岡市は台風の通過ルートから少し外れていることが多いため、直撃する頻度は少ないものの、台風周辺の強風や大雨の影響を受けることが多い地域です。特に西から東に向かって進む台風が多く、博多湾側から風が吹き込むケースが多いという特徴があります。
区別の台風対策ポイント
東区エリアの特徴と対策
特徴:
- 海に近いエリアがあり、潮風の影響を受けやすい
- 丘陵地も多く、風の通り道になりやすい場所がある
リフォーム福岡市東区でのポイント:
- 耐塩害性の高い素材選択が重要
- 風の通り道となる地形では両側支持タイプを推奨
- 香椎浜や和白などの海沿いでは特に注意が必要
博多区・中央区エリアの特徴と対策
特徴:
- 建物が密集し、風の流れが複雑
- ビル風の影響で局所的に強風が発生することも
リノベーション福岡市でのポイント:
- 周囲の建物との位置関係を考慮した設置
- ビル風の影響を受けやすい場所では固定を強化
- 都市部特有の飛来物リスクへの対応も必要
南区・城南区・早良区・西区エリアの特徴と対策
特徴:
- 山間部と平野部があり、地形による風の違いが大きい
- 西区は特に海に近く、台風の影響を受けやすい
リフォーム福岡市南区などでのポイント:
- 西区など海に近いエリアでは特に強度を重視
- 早良区や城南区の山沿いでは風の吹き下ろしに注意
- 南区の平野部では飛来物対策も重要
このように、福岡市内でもエリアによって最適な対策が異なります。リフォームやリノベーションの際には、地域特性を熟知した専門業者に相談することをおすすめします。
まとめ:カーポートの台風対策

カーポートの台風対策は、構造の特性を理解し、適切な方法で実施することが重要です。最後に、ポイントをまとめます。
台風対策の重要ポイント
1.カーポートの構造を理解する
・屋根は意図的に外れやすく設計されている
・片側支持タイプは特に補強が必要
・無理な固定は逆効果になることも
2.事前の対策を行う
・新規設置時は台風に強い製品を選ぶ
・既存のカーポートは適切な補強を検討
・定期的な点検でビスの緩みなどを確認
3.台風直前の緊急対策を実施
・周囲の小物を片付ける
・可能であれば屋根材を取り外す
・着脱式サポートの設置を検討
4.被害が出た場合の適切な対応
・被害状況を記録
・保険の適用を確認
・専門業者に修理を依頼
最後に
台風対策は「事前の備え」が何よりも重要です。台風シーズン前の点検や、新規設置時の慎重な製品選びが、将来の被害を大きく左右します。特に福岡市など台風の影響を受けやすい地域では、地域特性に合わせた対策が必要です。
万が一の被害を最小限に抑えるためにも、この記事を参考に、ご自宅のカーポートの状態を今一度確認し、必要な対策を講じていただければ幸いです。