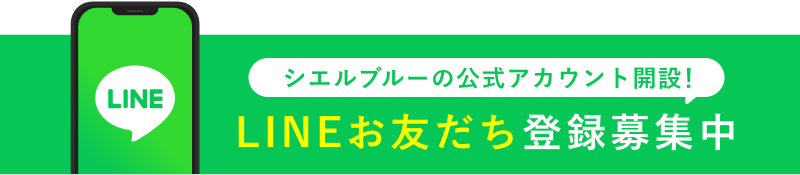リフォームノウハウ
畳の張替え工事で失敗しないための攻略法!福岡で工事をお願いするなら?

畳の表面が傷んできて、そろそろ張替えを検討している方も多いのではないでしょうか。でも、いざ調べてみると「裏返し」「表替え」「新調」など、聞き慣れない用語が並んで困惑してしまいますよね。
実は畳の張替えには3つの方法があり、それぞれ適切なタイミングと費用が大きく異なります。間違った選択をしてしまうと、無駄な出費につながったり、すぐにまた張替えが必要になったりすることも。
この記事では、畳張替えの基本知識から費用相場、最適なタイミングまで、失敗しないための情報をすべてシエルブルー高橋の経験からお伝えします。福岡市での畳張替えを検討している方にとって、きっと役立つ内容になっています。
目次
畳張替えの3つの方法と適用タイミング

畳の張替えには「裏返し」「表替え」「新調」の3つの方法があります。どの方法を選ぶかは、現在の畳の状態と使用年数によって決まります。
裏返し:2~5年目に適用
裏返しは、既存の畳表を文字通り裏返して再利用する方法です。畳表の表面が日焼けや擦れで傷んでも、裏面はまだきれいな状態を保っています。
この方法では畳縁も新しくなるため、見た目の印象はかなり改善されます。畳を新調してから2~5年程度で、表面の光沢が失われたり軽い日焼けが目立つようになったら、裏返しの検討時期です。
ただし、裏面にもシミや変色が見られる場合や、すでに5年以上使用している畳には適用できません。また、化学繊維製の畳表では裏返しができないケースもあります。
表替え:4~7年目に適用
表替えは、畳表と畳縁を新品に交換する方法です。畳床(畳の芯材)はそのまま使用するため、踏み心地は変わりませんが、見た目は新品同様になります。
裏返しを一度行った畳なら、そこから4~5年後が表替えの目安です。初回の畳から直接表替えする場合は、4~7年程度が適切なタイミングとなります。
畳表面のささくれが衣服に付着するようになったり、イグサの香りが失われたりした時は、表替えを検討すべき状況です。
新調:10~15年目に適用
新調は畳表、畳床、畳縁すべてを新品に交換する方法です。完全に新しい畳になるため、見た目も踏み心地も香りも一新されます。
使用開始から10~15年が新調の目安時期です。畳がへこんでクッション性が失われたり、ダニが気になったりする場合は、新調が最適な選択となります。
畳の構造を理解して適切な判断を

畳張替えの選択肢を理解するには、畳の基本構造を知っておくことが重要です。
畳表(たたみおもて)
畳表は、イグサを経糸(麻または綿)に織り込んだゴザ状の表面材です。畳の機能性の多くは、この畳表が担っています。
イグサには調湿効果、空気浄化効果、そして独特の香りによるリラクゼーション効果があります。品質は使用するイグサの本数や産地、経糸の材質によって決まり、国産イグサの方が一般的に品質が高いとされています。
最近では、和紙や樹脂を使った人工畳表も登場しており、耐久性やメンテナンス性に優れた製品も選択できます。
畳床(たたみどこ)
畳床は畳の芯材で、畳のクッション性を決める重要な部分です。従来は稲藁を圧縮した藁床が主流でしたが、現在は軽量化やダニ対策を考慮した建材床や藁サンド床も普及しています。
藁床は調湿性や復元性に優れていますが、重量があるのが特徴です。一方、建材床は軽量でダニが発生しにくく、マンションなどでは特に重宝されています。
畳縁(たたみべり)
畳縁は畳の側面に縫い付ける装飾的な生地です。畳表の保護と畳同士の隙間を埋める機能的な役割も担っています。
デザインは無地から柄物まで豊富に用意されており、部屋の雰囲気に合わせて選択できます。最近は化学繊維製の畳縁が主流で、耐久性とコストパフォーマンスに優れています。
畳張替え費用の詳細と価格差の理由

畳張替えにかかる費用は、選択する方法と材料のグレードによって大きく異なります。
裏返しの費用相場
裏返しの費用相場は1畳あたり約4,000円です。3つの張替え方法の中では最も経済的で、作業時間も短く済みます。
ほとんどの業者が畳を工場に持ち帰って作業するため、当日中または翌日には完成した畳が戻ってきます。費用に含まれるのは、畳縁代と作業工賃のみです。
表替えの費用相場
表替えの費用相場は1畳あたり5,000円~20,000円と、選択する畳表のグレードによって大きく変動します。
価格差の主な要因は以下の通りです
| グレード | 価格帯 | 特徴 |
| 普及品 | 5,000~8,000円 | 中国産イグサ、綿糸使用 |
| 中級品 | 8,000~12,000円 | 国産イグサ、綿糸使用 |
| 高級品 | 12,000~20,000円 | 国産イグサ、麻糸使用 |
マンション用の薄い畳は、一般的に戸建て用より安価になる傾向があります。また、人工畳表を選択した場合も価格帯が変わります。
新調の費用相場
新調の費用相場は1畳あたり10,000円~35,000円で、最も幅広い価格帯となります。畳表、畳床、畳縁すべての材料と工賃が含まれるためです。
高級品を選択した場合は、35,000円を超えることも珍しくありません。特に茶室用の特級品や、伝統的な藁床を使用した畳は高額になります。
作業期間は2~10日程度で、既存畳の採寸後に新しい畳を製作してから交換するため、施工期間中に畳がない状態にはなりません。
畳張替えに最適な季節とタイミング

畳張替えを行う時期は、畳の劣化状況だけでなく季節的な要因も考慮する必要があります。
春(3~5月)
春は引っ越しシーズンと重なり、畳張替えの需要が高まる時期です。新生活のスタートに合わせて畳を新調する家庭が多く、畳店の繁忙期でもあります。
国産イグサは前年の秋に乾燥させたものが出回る時期でもあり、品質の良い畳表が手に入りやすいというメリットがあります。ただし、需要が集中するため、工期が長くなる可能性があります。
夏(6~8月)
梅雨明け後からお盆にかけて、多くの家庭で畳張替えが行われます。湿気の多い梅雨時期を避けて発注する方が多いためです。
ただし、新しいイグサは湿気によるカビが発生しやすいため、湿度の高い時期の畳新調は避けた方が無難です。表替えや裏返しであれば、特に問題はありません。
秋(9~11月)
秋は畳張替えに最も適した季節の一つです。降雨量が少なく湿度も安定しているため、畳の状態が良好に保たれます。
夏の間にたまった床下の湿気を改善する効果もあり、家全体の環境改善につながります。年末の大掃除前に畳を整えておくというメリットもあります。
冬(12~2月)
空気が乾燥している冬は、実は畳張替えに非常に適した時期です。畳張替え中に床下も乾燥させることができ、カビやダニの発生を抑制できます。
特に2月は畳店の閑散期にあたるため、工期の希望が通りやすく、価格交渉もしやすい時期です。年末年始を避ければ、落ち着いて作業を依頼できます。
失敗しない業者選びのポイント

畳張替えの成功は、信頼できる業者選びにかかっています。
見積もりの透明性を確認
優良業者は、材料費と工賃を明確に分けて見積もりを提示します。「一式」表示で詳細が不明な業者は避けた方が賢明です。
また、複数社から見積もりを取る際は、同じグレードの材料で比較することが重要です。価格だけでなく、使用する畳表の産地や品質も確認しましょう。
実績と専門性をチェック
畳専門店か総合リフォーム会社かによって、専門性に差があります。畳に関する深い知識と豊富な経験を持つ業者を選ぶことで、適切なアドバイスを受けられます。
地域密着で長年営業している業者は、アフターサービスの面でも安心です。万が一のトラブルにも、迅速に対応してもらえる可能性が高いでしょう。
アフターサービスの内容確認
畳張替え後の保証期間や、メンテナンス方法の指導など、アフターサービスの内容も重要な判断基準です。
特に新調の場合は、1年程度の品質保証を設けている業者が安心です。また、定期的なメンテナンスサービスを提供している業者もあります。
畳張替えで避けるべき失敗パターン

実際によくある失敗例を知っておくことで、同じミスを避けることができます。
時期を逃した結果の高額出費
「まだ大丈夫」と思って放置した結果、裏返しで済んだものが表替えに、表替えで済んだものが新調になってしまうケースがあります。
定期的に畳の状態をチェックし、適切なタイミングで張替えを行うことが、長期的なコスト削減につながります。
安さだけで業者を選んだ失敗
極端に安い見積もりを提示する業者の中には、材料の質を下げたり、手抜き工事をしたりするところもあります。
価格と品質のバランスを考慮し、適正価格で信頼できる業者を選ぶことが重要です。
グレード選択のミス
使用環境に合わないグレードを選んでしまい、期待した耐久性が得られないケースもあります。
家族構成やライフスタイル、使用頻度などを業者に伝え、最適なグレードの提案を受けることが大切です。
賃貸住宅での畳張替えの注意点

賃貸住宅にお住まいの方は、畳張替えの費用負担について特に注意が必要です。
通常使用による劣化は貸主負担
国土交通省のガイドラインでは、経年劣化や通常使用による畳の傷みは、貸主が費用を負担することになっています。
日焼けによる色褪せや、普通に生活していて生じるけば立ちなどは、借主の負担にはなりません。
借主負担となるケース
一方で、借主の故意・過失による損傷は、借主が費用を負担する必要があります。
窓の締め忘れによる雨漏れ被害や、飲み物をこぼしたシミ、ペットによる傷などが該当します。
特約条項の確認
契約書に畳張替え費用を借主負担とする特約がある場合もあります。ただし、明らかに不当な特約は法的に無効となる可能性があります。
契約前に条項をしっかり確認し、疑問があれば専門家に相談することをお勧めします。
火災保険の適用可能性

意外に知られていませんが、畳張替えに火災保険が適用されるケースもあります。
水災・水濡れによる損傷
台風や洪水による水災、または給水設備の事故や上階からの水漏れによる水濡れで畳が損傷した場合、火災保険の対象となる可能性があります。
ただし、経年劣化やカビなどの自然発生する損害は補償対象外です。
畳は建物の補償対象
畳は家財ではなく建物の一部として扱われるため、建物の火災保険で補償されます。
偶発的な事故で畳張替えが必要になった場合は、保険会社に相談してみることをお勧めします。
畳の寿命を延ばす日常メンテナンス
適切なメンテナンスにより、畳の寿命を大幅に延ばすことができます。
日常的な掃除方法
畳の目に沿って掃除機をかけることが基本です。目に逆らうとイグサが傷む原因となります。
乾いた雑巾での乾拭きも効果的で、水拭きは畳表を傷める可能性があるため避けましょう。
湿度管理の重要性
室内湿度を50~60%程度に保つことで、畳の調湿効果を最大限活用できます。
エアコンや除湿器を上手に使い、極端な高湿度や低湿度を避けることが大切です。
家具の配置と荷重分散
重い家具を長期間同じ場所に置くと、畳がへこんで回復しなくなります。
定期的に配置を変えたり、家具の下に板を敷いたりして荷重を分散させましょう。
福岡市での畳張替え:地域特性を活かした選択

福岡市で畳張替えを検討する際は、地域特有の気候条件を考慮することが重要です。
福岡市の気候特性と畳選びの基本
福岡市は温暖湿潤気候で、夏は高温多湿、冬は比較的温暖です。年間降水量も多く、梅雨時期の湿度対策が特に重要になります。
このような気候条件では、調湿効果の高い国産イグサや、カビ・ダニに強い人工畳表が適しています。また、建材床やサンド床など、湿気に強い畳床の選択も有効です。
湿度が高い時期の新調は避け、乾燥した冬場や梅雨明け後の時期を選ぶことで、より良い状態で畳を使い始めることができます。
各区の特性を活かした畳選び
東区エリアでは、海に近い立地のため塩分を含んだ風の影響を受けやすく、畳表の選択には特に注意が必要です。耐久性の高い国産イグサや、化学繊維製の畳表を検討することをお勧めします。また、古い住宅が多いエリアでは、畳床の状態確認も重要なポイントです。
博多区エリアは都市部で住宅密度が高く、マンションタイプの薄い畳を使用している住宅が多いのが特徴です。軽量で施工が容易な建材床を使った畳が人気で、コストパフォーマンスを重視した選択がよく行われています。
中央区エリアでは、高級住宅やマンションが多く、デザイン性の高い畳縁や、上質な国産イグサを使った畳表のニーズが高いエリアです。琉球畳のような縁なし畳への変更相談も多く見られます。
南区エリアは戸建て住宅が多く、伝統的な畳の使用が継続されているエリアです。表替えや新調の際も、従来通りの藁床や国産イグサにこだわる家庭が多いのが特徴です。春日市との境界部では、住宅の築年数も比較的新しく、メンテナンス需要が安定しています。
城南区エリアは住宅地として人気が高く、子育て世代の家庭が多いエリアです。そのため、ダニやカビに強い人工畳表や、汚れに強い撥水加工された畳表の需要が高くなっています。
西区エリアは新しい住宅開発が進んでいるエリアで、新築時から畳の選択肢を検討する機会が多くあります。モダンなインテリアに合わせた畳選びや、メンテナンス性を重視した材料選択の相談が特に多いエリアです。
福岡市内でリフォームやリノベーションを検討されている方は、地域の気候特性と住環境を理解した地元の専門業者に相談することで、最適な畳選びができるでしょう。東区をはじめとする各エリアの特性に応じたアドバイスを受けることが、長期的な満足度向上につながります。
まとめ
畳の張替えは、適切なタイミングと方法を選択することで、コストを抑えながら快適な住環境を維持できます。
重要なポイント:
- 2~5年で裏返し(4,000円/畳)
- 4~7年で表替え(5,000~20,000円/畳)
- 10~15年で新調(10,000~35,000円/畳)
畳の状態を定期的にチェックし、適切な時期に張替えを行うことが経済的です。業者選びでは価格だけでなく、専門性やアフターサービスも重視しましょう。
福岡市での畳張替えをお考えの方は、地域の気候特性を理解した地元の専門業者に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、長く愛用できる畳選びができるはずです。