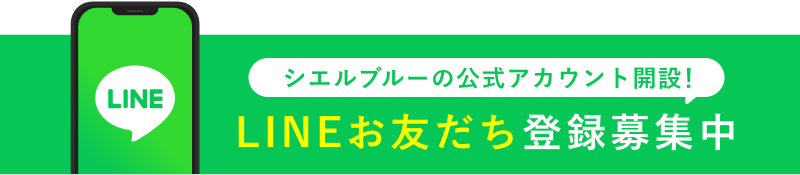その他
リフォームローンで住宅ローン控除を受ける完全ガイド【2025年最新版】

リフォームを検討していて、「住宅ローン控除って使えるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。実は、リフォームでも条件を満たせば住宅ローン控除が適用できるんです。
最大140万円もの控除が受けられる制度を見逃すのはもったいないですよね。今回は、リフォームローンの住宅ローン控除について、適用条件から具体的なメリット、申請方法まで詳しく解説していきます。
目次
リフォームローンでも住宅ローン控除が使える理由
住宅ローン控除といえば、新築住宅の購入時に利用するイメージが強いかもしれません。しかし、実際にはリフォーム工事でも適用可能な制度なんです。
この制度の背景には、国が住宅の質向上や長寿命化を推進したいという狙いがあります。古い住宅を快適で安全な住まいにアップグレードすることで、住宅ストック全体の価値向上を図っているんですね。
つまり、あなたがリフォームを行うことは、国の政策にも合致した行動なのです。だからこそ、税制面でのメリットが用意されているというわけです。
住宅ローン控除の基本的な仕組み

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度です。リフォームローンの残高に応じて、毎年一定額が所得税や住民税から控除される仕組みになっています。
控除期間は10年間で、毎年末のローン残高の0.7%が控除されます。所得税から控除しきれない分については、住民税からも一部控除が可能です。
例えば、1,000万円のリフォームローンを組んだ場合、1年目は約7万円の控除を受けられる計算になります。これが10年間続くわけですから、かなりのメリットがありますよね。
控除を受けられるリフォーム工事の種類
住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事は、国税庁によって明確に定められています。どのような工事が対象になるのか、具体的に見ていきましょう。
大規模な増築・改築・模様替え
建物全体に関わるような大がかりなリフォームが対象となります。増築工事では部屋を追加したり、建物面積を拡張する工事が該当します。また、建物の骨組みだけを残して全面改修するスケルトンリフォームや、住宅全体を新築同様に改修するフルリフォームも対象です。
ただし、一部屋だけのクロス張り替えなど、小規模な工事は対象外となる点にご注意ください。国税庁では「大規模な修繕又は模様替え」という表現を使っており、建築基準法に規定される一定の規模以上の工事が必要となります。
マンション等の区分所有建物の修繕
マンションの専有部分について、床、階段、壁の過半数以上をリフォームした場合が対象です。「過半数以上」というのがポイントで、50%未満の工事では控除を受けられません。
例えば、マンション全体のフローリング張り替えと壁紙の全面貼り替えを同時に行う場合は、過半数の条件を満たすため控除対象となります。しかし、リビングだけのフローリング張り替えでは、条件を満たさない可能性があります。
一室全体のリフォーム
戸建て住宅やマンションで、特定の部屋全体をリフォームする場合も対象となります。対象となる部屋は、居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下などです。
これらの部屋の床または壁の全部について修繕・模様替えを行った場合に適用されます。部分的な工事ではなく、その部屋全体を改修する必要があるという点が重要です。
特定の目的を持つリフォーム工事
社会的なニーズの高い特定の工事については、規模に関係なく対象となる場合があります。
耐震改修工事では、現行の耐震基準を満たすための補強工事が対象です。基礎の補強、壁の補強、接合部の強化などが含まれます。1981年(昭和56年)以前に建築された住宅は、旧耐震基準で建てられているため、耐震改修工事の対象となることが多いです。
バリアフリー改修工事は、高齢者や障害者の方が安全に生活できるようにする工事です。手すりの設置、段差の解消、通路の拡幅、床材の滑り止め加工、エレベーターの設置などが該当します。
省エネ改修工事では、住宅の省エネ性能を向上させる工事が対象となります。窓や玄関ドアの断熱化、壁・床・天井の断熱工事、高効率空調機の設置、太陽光発電設備の設置などが含まれます。
住宅ローン控除を受けるための条件

リフォームで住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。まず、自分名義の物件であることが基本条件です。借地上の建物や賃貸住宅では適用されません。
居住開始については、工事完了から6ヶ月以内に居住を開始し、控除申請年の12月31日まで引き続き住んでいる必要があります。リフォーム後の床面積は50㎡以上である必要があり、これは登記簿上の面積で判断されます。
所得制限として、控除申請年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。工事費用については、補助金等を差し引いて100万円を超える必要があり、ローンの返済期間は10年以上でなければなりません。
| 項目 | 条件 |
| 所有者 | 自分名義の物件であること |
| 居住開始 | 工事完了から6ヶ月以内に居住開始 |
| 床面積 | リフォーム後の床面積が50㎡以上 |
| 所得制限 | 控除申請年の合計所得金額が2,000万円以下 |
| 工事費用 | 補助金等を差し引いて100万円超 |
| ローン期間 | 返済期間が10年以上 |
店舗や事務所を併設している併用住宅の場合は、居住部分の工事費が全体の工事費の1/2以上である必要があります。これは、あくまでも住宅としての利用が主体であることを示すための条件です。
控除額の上限と計算方法
リフォームの住宅ローン控除には上限が設定されています。控除期間は10年間で、年間控除額は最大14万円、控除期間全体での上限は140万円となっています。控除率は年末ローン残高の0.7%です。
この控除率は、新築住宅の購入時と同じ率が適用されるため、リフォームでも新築と同等の優遇を受けられることになります。ただし、年間の控除額には上限があるため、非常に高額なリフォームローンを組んだ場合でも、上限を超える控除は受けられません。
控除額の計算は非常にシンプルです。毎年12月31日時点のローン残高に0.7%を掛けた金額が、その年の控除額となります。この金額がまず所得税から控除され、所得税から控除しきれない分については、住民税から最大13.65万円まで控除されます。
実際の控除額をシミュレーション
具体的な数字で控除額を見てみましょう。1,500万円のリフォームローンを組んだ場合を想定すると、毎年100万円ずつ返済していくとして、1年目のローン残高は1,400万円になります。この場合の控除額は9.8万円となります。
2年目にはローン残高が1,300万円となり、控除額は9.1万円に減少します。このように毎年ローン残高の減少に伴って控除額も減っていき、10年間の合計では約66万円の控除を受けられる計算になります。
| 年 | ローン残高(万円) | 控除額(万円) |
| 1年目 | 1,400 | 9.8 |
| 2年目 | 1,300 | 9.1 |
| 3年目 | 1,200 | 8.4 |
| 4年目 | 1,100 | 7.7 |
| 5年目 | 1,000 | 7.0 |
| 合計(10年間) | – | 66.5 |
800万円の比較的小規模なリフォームローンの場合でも、10年間で37万円の控除を受けられます。これは決して小さな金額ではありませんよね。家計にとって大きなメリットとなることがお分かりいただけると思います。
併用可能な他の減税制度
住宅ローン控除以外にも、リフォームで利用できる減税制度があります。条件が合えば併用も可能で、さらなる税制メリットを受けることができます。
リフォーム促進税制では、耐震、省エネ、バリアフリー、長期優良住宅化リフォームが対象となります。最大控除額は25万円で、控除期間は1年間(工事完了年のみ)、控除率は工事費の10%です。
固定資産税の減税も見逃せません。耐震リフォームを行った場合は1年間1/2に軽減され、省エネリフォームやバリアフリーリフォームの場合は1年間1/3に軽減されます。これらの制度は住宅ローン控除と併用可能なので、該当する工事を行う場合は忘れずに申請しましょう。
特に耐震リフォームについては、住宅ローン控除との併用効果が高く、トータルでの節税効果が大きくなる傾向があります。築年数の古い住宅をお持ちの方は、耐震性能の向上と税制メリットの両方を得られるため、積極的に検討する価値があります。
確定申告の手続きと必要書類

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必須です。申告漏れがないよう、しっかりと準備しましょう。申告期間は毎年2月16日から3月15日まで、対象年度はリフォーム工事が完了し、居住を開始した年の翌年からです。
会社員の方には特例があり、初年度だけ確定申告を行えば、2年目以降は年末調整で手続きできます。これは新築住宅の場合と同じ取り扱いで、手続きの負担が軽減されています。
確定申告には多くの書類が必要です。基本的な書類として、確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書、工事請負契約書の写し、増改築等工事証明書、源泉徴収票(給与所得者の場合)が必要となります。
補助金を受けた場合は、補助金決定通知書や補助金等の額を証する書類も追加で必要です。また、贈与を受けた場合は、贈与税の申告書等や住宅取得等資金の額を証する書類も準備する必要があります。
書類の入手先は様々で、リフォーム業者からは工事請負契約書や増改築等工事証明書を、金融機関からは年末残高等証明書を、法務局からは登記事項証明書を、市区町村からは住民票を、勤務先からは源泉徴収票をそれぞれ入手します。
制度利用時の注意すべきポイント

制度を利用する際の注意点を把握しておくことで、後でトラブルになることを防げます。まず、控除額は毎年減少するという点です。住宅ローン控除は年末のローン残高に基づいて計算されるため、ローンを返済するにつれて控除額も減少します。
家計の収支計画を立てる際は、この点を考慮に入れておくことが重要です。「今年は10万円控除されたから、来年も10万円だろう」という認識は誤りで、残高が減る分、控除額も減ってしまいます。
確定申告は自己責任で行う必要があります。控除は自動的に適用されるものではなく、期限内に確定申告を行わなければ、控除を受ける権利を失ってしまいます。特に個人事業主の方は、毎年の申告が必要となるため、忘れずに手続きを行いましょう。
所得税額を超える控除は翌年に繰り越すことができません。その年の所得税額を超える控除額があっても、翌年に繰り越すことはできませんが、住民税からの控除(上限13.65万円)は利用できます。
住宅ローン控除を受けた住宅を売却する際の影響も考慮しておく必要があります。売却時には、取得費から控除額を差し引いて譲渡所得を計算する場合があるため、将来の売却予定がある方は事前に税理士等に相談することをおすすめします。
リフォーム業者選びのポイント
住宅ローン控除を最大限活用するためには、適切な業者選びも重要です。制度に詳しい業者を選ぶことで、控除対象となる工事の要件を正しく理解した提案を受けることができ、必要な証明書類の発行にもスムーズに対応してもらえます。
複数社での相見積もりは必須です。同じ工事内容でも、業者によって費用は大きく異なります。必ず複数社から見積もりを取って比較検討しましょう。その際、工事費用が100万円を超えるかどうか、控除対象となる工事内容が含まれているかどうかも確認することが大切です。
アフターサービスの充実も重要な選択基準です。リフォーム後のメンテナンスや不具合対応も考慮して業者を選ぶことで、長期的に安心して住み続けることができます。特に住宅ローン控除は10年間の長期制度のため、その間のサポート体制も確認しておきましょう。
福岡市の気候特性を活かしたリフォーム計画

福岡市は温暖湿潤気候で、夏は高温多湿、冬は比較的温暖という特徴があります。この気候条件を考慮したリフォーム計画を立てることで、より快適な住環境を実現できます。
博多湾に面した地域では塩害対策も重要です。外壁や屋根の材料選択の際は、耐食性の高い素材を検討することをおすすめします。また、福岡市は台風の影響を受けやすい地域でもあるため、窓や外壁の強化、雨漏り対策などの工事は、住宅ローン控除の対象となる耐震・耐風改修工事として認められる場合があります。
湿度が高い地域特性を考慮すると、断熱性能の向上と併せて換気性能の向上も重要です。これらの工事は省エネ改修工事として住宅ローン控除の対象となるため、快適性の向上と税制メリットの両方を得ることができます。
各区の特性を活かした窓選び
東区エリアでよくある相談内容と解決策 東区は住宅地が多く、ファミリー層からの断熱性能向上の相談が多く見られます。特に海の中道や香椎浜周辺では、海からの潮風対策として樹脂サッシへの交換リフォームが人気です。このような工事は住宅ローン控除の省エネ改修工事として認定されるため、税制面でもメリットがあります。
博多区エリアの特徴と対応ポイント 博多区はオフィス街と住宅地が混在する地域で、騒音対策として防音性の高い窓へのリフォームニーズが高くなっています。これも住宅ローン控除の対象となる場合があり、築年数の古いマンションでは、結露対策を含めた総合的な窓リフォームが効果的です。
中央区エリアならではの考慮点 中央区は福岡市の中心部で、マンションでのリフォームが中心となります。管理規約の制約がある中でも、内窓の設置や断熱フィルムの施工など、住宅ローン控除を活用できる省エネリフォームの選択肢があります。
南区エリアの住宅事情と推奨プラン 南区は戸建て住宅が多い地域で、築30年以上の住宅からの相談が多く見られます。窓の全面交換と合わせて外壁断熱も行うことで、住宅ローン控除の上限額を最大限活用できるプランをご提案することが多いです。
城南区エリアの特性と注意点 城南区は文教地区として知られ、長期間居住される方が多い地域です。バリアフリー性能を考慮した窓の高さ調整や開閉方式の変更など、将来を見据えたリフォームが人気で、これらもバリアフリー改修工事として住宅ローン控除の対象となります。
西区エリアの環境に応じた提案 西区は海に近い地域が多く、塩害や強風への対策が重要です。耐風圧性能の高い窓への交換や、雨戸・シャッターの電動化なども含めたリフォームプランで、住宅ローン控除を効果的に活用できます。
まとめ
リフォームローンの住宅ローン控除は、適切に活用すれば大きな節税効果を得られる制度です。最大140万円の控除を受けられる可能性があることを考えると、リフォーム計画の検討段階から制度の活用を前提とした設計をすることが重要です。
ただし、制度の適用には細かな条件があり、確定申告などの手続きも必要です。工事の種類、費用、ローンの条件など、様々な要素が絡み合うため、事前の計画と準備が欠かせません。
リフォームを検討される際は、制度に詳しい専門業者に相談することをおすすめします。特に福岡市でリフォームをお考えの方は、地域の気候特性や住宅事情を踏まえた提案ができる地元業者との相談が効果的です。住宅ローン控除を最大限活用しながら、快適で価値の高い住まいを実現してください。